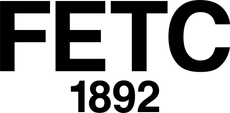緑茶・ほうじ茶・紅茶・烏龍茶など、お茶にはいろんな種類がありますよね。それぞれ全く違った楽しみ方ができるお茶ですが、今回はそんな「日本茶」についてのお話です。
日本茶って?
「日本茶」とは文字通り、日本国内で生産されるお茶の総称ですが、その種類は多岐に渡ります。日本で最も広く飲まれている煎茶や、香ばしい香りが特徴のほうじ茶、海外でも人気の高い抹茶などが一般的ですが、実は紅茶や烏龍茶も日本国内で生産されている事はご存知でしたか?
そもそも、緑茶も紅茶も烏龍茶も、育て方や加工方法が違うだけで全て同じお茶の木から生まれるんです!
この記事では、皆さんが普段飲んでいるお茶の種類と、意外と知られていないその違いについてご紹介します。
お茶の種類は何で変わる?
煎茶も紅茶も烏龍茶も同じ茶葉からできるのだとしたら、その違いはどこから生まれるのでしょう?
それは、『茶葉の発酵(酸化)の度合い』の違いです。
この「発酵」について補足しておくと、お茶の世界では「発酵」という言葉をよく使うのですが、厳密には「発酵」とは微生物が作用して性質が変化することであり、微生物を使って茶葉を発酵させて作られるのはプーアール茶などの後発酵茶のみです。それ以外の場合、正確には酸化酵素による「酸化」と呼ぶのが正しいのですが、一般的な表現に合わせてここでは「発酵」という言葉を使います。
茶葉は摘み取られたその瞬間から発酵が始まります。この発酵によって茶葉の色や味わい、香りが変化していき、発酵をさせずに加工したものが煎茶(不発酵茶)、半分発酵させたものが烏龍茶(半発酵茶)、最後まで発酵させたものが紅茶(発酵茶)となります。
もちろん品種や育て方によって、紅茶に適した茶葉や煎茶に適した茶葉はありますが、元の植物は全て同じ「チャ」の木から生まれるのです。
お茶の種類
それでは、それぞれのお茶がどんなお茶なのか、一つずつ見ていきましょう。
不発酵茶
まずはほとんど茶葉を発酵させずに作られる不発酵茶。収穫後すぐに茶葉の発酵を止めることで、茶葉の緑色が保たれ、私たちに馴染み深い緑色のお茶になるのです。 不発酵茶=緑茶だと考えてください。
煎茶
煎茶は日本人にとって最も馴染み深く、国内で最も生産量の多いお茶です。
緑茶の風味は普通、食べ物と同様に旨味・甘味・渋味・苦味で表現されますが、煎茶は渋味・甘味のバランスがよく、澄んだ緑色が特徴のお茶です。
皆さんが日本茶と言われて思い浮かべるのは多くの場合、この煎茶でしょう。
深蒸し煎茶
深蒸し煎茶は煎茶の種類の一つで、茶葉を加工する過程で行われる「蒸し」の時間を2〜3倍に長くしたお茶です。煎茶の7割程度は、この深蒸し煎茶として生産されています。
深く蒸す分、茶葉が柔らかく細かくなり、通常の煎茶と比べて水色も味も濃く出るのが特徴です。
玉露
とろりとした旨味と爽快な香りが特徴的な玉露は、日本茶の中でも最高級のお茶です。
玉露は収穫前に20日間以上、茶葉に太陽光を当てないように覆いをして育てられます。茶葉の旨味成分である「テアニン」は、太陽光によって渋味成分である「カテキン」へと変化してします。長い期間太陽光を遮ることで、茶葉の旨味成分が渋味成分に変わるのを防ぐことができ、マイルドな渋味と濃厚な旨味を持つお茶が出来上がるのです。
また、この被覆栽培によって茶葉には、「覆い香」と呼ばれる海苔のような香りも追加されます。この覆い香は玉露や抹茶の特徴的な香りとなっており、高級茶の証拠とも言われています。
水色、香り、味。どれを取っても極上の緑茶といえます。
かぶせ茶
玉露が20日間以上の被覆栽培で作られるのに対し、かぶせ茶は7〜10日間前後の被覆栽培で作られます。50〜60度で淹れると玉露のような旨味が、70度程度で淹れると煎茶のようなバランスの良いお茶が楽しめるお茶です。
価格帯もちょうど玉露と煎茶の中間くらいのお茶なので、ちょっと良いお茶が飲みたい時などにぴったりです。
抹茶
近年フランスやアメリカでブームになっている抹茶は、原料となる碾茶(てんちゃ)を石臼で挽いて作られます。碾茶自体は玉露と同じように、20日間以上被覆栽培をして作られますが、加工の際に茶葉を蒸した後、ひたすら乾燥させて作られるのが特徴です。
茶筅で点てて飲む抹茶は、儀式的な美しさもそうですが、お湯に溶け出さない不水溶性成分も全て取り込むことができるというメリットもあります。
京都の宇治を筆頭に、静岡や三重でも作られています。
茎茶・棒茶
茶の葉の部分ではなく、茎の部分を使ったのが茎茶です。地域によっては棒茶と呼ぶこともあります。特に高級な煎茶や玉露の茎茶は「白折(しらおれ)」と呼ばれ、京都では玉露の茎茶は「雁ヶ音(かりがね)」と呼ばれています。
実はお茶の茎には旨味成分であるテアニンが豊富に含まれており、しっかりした旨味があり、尚且つ茶葉ではない部分を使っているので価格が安く、日常使いに適したお茶です。
釜炒り茶
茶葉を蒸す代わりに、釜で炒ることで茶葉の酸化を止めて作られるのがこの釜炒り茶。中国で生まれた製法で、炒ることで青臭さが消え、「釜香」と呼ばれる香ばしい香りが追加されるのでさっぱりと飲みやすいお茶です。
煎茶と違い、茶葉の形を整える精揉(せいじゅう)のプロセスが無いため、茶葉がぐりっとカールしているのも特徴です。
日本では九州の佐賀 嬉野市を中心に作られています。
番茶
5月に収穫される一番茶の後、6月〜7月に摘まれる二番茶・三番茶や9月に摘まれる秋冬番茶のことを番茶(晩茶とも)と呼びます。茶葉だけではなく、茎を使う場合もあります。
夏の強い日差しの下で育った茶葉は、渋味成分であるカテキンが多く、逆に旨味成分であるアミノ酸の含有量が少ないお茶となります。煎茶や玉露とは違い、渋味や苦味が引き立った、キレのある飲みやすさが特徴です。
最近では価格の安さから、ペットボトルのお茶にも利用されています。
上の写真は番茶の茎の部分を焙じたお茶です。
ほうじ茶
ほうじ茶は文字通り、緑茶の茶葉を焙じることで香ばしい香りを付加したお茶です。焙じることでカテキンが不溶性成分となり、苦味・渋味成分が少なく、身体への刺激が少ないお茶になります。
一般的に、ほうじ茶には番茶や茎茶が使われるので価格も安く、口当たりもさっぱりしているので食事中のお茶に選ばれることも多いお茶です。
玄米茶
お茶と炒り米をブレンドして作られる玄米茶は、炒った米の香ばしさが特徴のお茶です。ほうじ茶同様、香りをプラスして作られるお茶なので、番茶を使うのが一般的です。
発酵茶
お茶の中で、茶葉を発酵させる度合いが最も高いのが発酵茶(紅茶)です。発酵が進むことによって茶葉の色や香りが変化し、苦味・渋味が際立つお茶になります。
紅茶
茶葉の発酵を最小限にとどめて作られる煎茶に対して、発酵を最も進ませてから作られるのが紅茶です。
日本では「お茶」といえば緑茶ですが、実は全世界で作られるお茶の約70%は紅茶です。イギリスをはじめとし、世界のお茶のスタンダードは圧倒的に紅茶なのです。インドのダージリン、中国のキームン、スリランカのウバが三大産地として有名です。
私たちが取り扱っているのは日本産の紅茶で、和紅茶とも呼ばれています。世界的に見ればまだまだ生産量は小さいですが、海外産の紅茶とも比肩する美味しい紅茶もたくさんあります。
半発酵茶
中国・台湾での生産が盛んな半発酵茶は、茶葉の発酵によって独特の香りを引き出します。発酵の進み度合いによって白茶・黄茶・烏龍茶・黒茶といった分類がされていて、緑茶の酵発度を0、紅茶の発酵度を100とするならば、30〜70のものが半発酵茶となります。
烏龍茶
前述の例えでいえば、70くらいの発酵度で作られるのが烏龍茶です。
日本よりも中国や台湾での生産量が圧倒的に多く、発酵の度合いによって緑茶に近いものや紅茶に近いものもあります。
後発酵茶
ここまででご紹介した 不発酵茶・発酵茶・半発酵茶はいずれも、茶葉の酸化酵素による「酸化」で作られるお茶でしたが、後発酵茶は乳酸菌などの微生物によって茶葉の性質を変化させる、本当の意味での「発酵」で作られるお茶です。
中国のプーアール茶や徳島の阿波番茶、高知の碁石茶など、使用する微生物や地域によって様々な種類があります。
プーアール茶
プーアール茶は、中国で盛んに作られている、麹菌によって数ヶ月以上発酵させて作ったお茶です。発酵によって生まれる土を連想させるような独特の香りと、発酵の過程でカテキンが重合カテキンという渋味の薄い成分に変化することで生まれる、まろやかな味わいが特徴です。
長期保存が可能なため、年代物のプーアール茶も存在し、ヴィンテージワインのように高価なものも存在します。
お茶の種類がわかると、お茶はもっと美味しい
以上、日本で消費量の大きいお茶の種類と違いをご紹介しました。それぞれのお茶ごとに、全く違った味わいと楽しみ方があるので、好きなお茶を探してみてください!