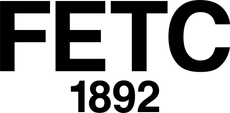私たちが普段飲んでいる緑茶・紅茶・烏龍茶など、味も香りも色も異なるこれらのお茶が、全て同じ茶葉から作られているのを知っていますか?
これらのお茶が異なる味わいや香りを持つのは、製造方法の違いによるものです。
今回は、烏龍茶などの中国茶を始めとする「半発酵茶」の、製造工程や製法について詳しく解説していきます。
半発酵茶(中国茶)の製造工程の特徴
「半発酵茶」とは、発酵を途中で止めて作られるお茶をいいます。
元々お茶の生葉には酸化酵素が含まれていて、収穫後からその酵素の働きで酸化発酵が起こります。その発酵を、頃合いのいい頃に加熱処理によって止めることで、独自の色や風味を引き出したのがこの半発酵茶です。
発酵と酸化?
お茶の世界で使われる発酵とは、味噌やヨーグルトのように微生物(菌)によって起こる発酵とは違い、茶葉のもつ酸化酵素よって起こる酸化のことを指しています。
酸化とは、酸素と酵素が結びついて、もとの成分を変化させる反応をいいます。
一部、後発酵茶のように微生物の力で発酵させるお茶もありますが、基本的にお茶業界では酸化を発酵と呼んでいます。
半発酵茶の種類と違いについて
半発酵茶は、発酵の度合いで種類が分かれます。その種類について解説します。
半発酵茶の種類
- 白茶:白牡丹、銀針白毫 など
- 黄茶:君山銀針、蒙頂黄芽 など
- 青茶:烏龍茶、鉄観音茶 など
発酵度合いの違い
白茶
「白茶」は、茶葉が育って間もない、白毛の取れないうちに収穫された茶葉を使って作られるお茶です。発酵時間が短く、半発酵茶の中で唯一「揉捻」という作業を行わないことが特徴です。
黄茶
「黄茶」は、荒茶の工程中に軽い発酵を行って作られるお茶です。加熱処理後に茶葉に残った熱と湿気を利用して発酵を行う「悶黄」という工程があります。
青茶
「青茶」は、半発酵茶を代表する種類のお茶です。烏龍茶はこの青茶に分類されます。
発酵が進んで茶褐色になった茶葉と、不発酵でまだ緑色を保った茶葉が混じっている様子から「青茶」と呼ばれています。
収穫された生葉が出荷されるまで
どのお茶にもおいてもまず「摘採」といわれるお茶の葉を収穫するところからお茶作りは始まります。中国茶は日本のお茶と違い、開き具合の大きい茶葉を収穫していくのが特徴です。収穫された茶葉は、萎凋や発酵、揉捻、乾燥などを経て「荒茶」へと加工され、その後仕上げ加工が行われてから出荷されます。
荒茶ができるまで
茶種によって様々な工程がありますが、一般的な烏龍茶の製法を例に挙げると、「日干萎凋(晒青) → 室内萎凋(涼青) →回転発酵(揺青) →釜炒り(殺青)→ 締め揉み(包揉) → 揉捻 → 乾燥」という工程を経て「荒茶」となります。
1. 日干萎凋(晒青)
晴天時に日に当てて干し、お茶の葉をしおれさせる作業を行います。天候が悪い時には萎凋槽で熱風を当てて処理しますが、一般に天日に当てて干したものが品質が良いとされています。
2. 室内萎凋(涼青)
日干萎凋を行うと茶葉の温度が上がるため、一度室内の棚に広げて静かに冷まし、その後次の工程に入ります。
3. 回転発酵(揺青)
竹かごの中に茶葉を入れて回転させ、茶葉の周囲に傷を付けていきます。傷のついた部分から酸化発酵が活発になり、茶葉の周りは茶褐色、真ん中は緑色を保ったままの半発酵状態になります。
4. 釜炒り(殺青)
ちょうど良い発酵具合を見極め、釜で炒って殺青します(茶葉の酸化酵素を失活させて発酵を止めること)。斜め釜を用いて手で炒る方法が主流ですが、最近では機械化も進んでいます。
5. 揉捻
日本茶などと同様に圧力をかけて茶葉を揉みます。茶葉の水分を均一化させるとともに、茶葉の成分を抽出しやすくします。
6. 締め揉み(包揉)
風呂敷ほどの大きさの布に茶葉を包み、転がすように茶葉を絞りながら締めて形を整えます。この作業と次の工程である乾燥を20回ほど繰り返していきます。
7. 乾燥
きつく締めた茶葉の塊をほぐした後、茶葉の水分を抜くために乾かします。一気に乾いて茶葉の形が元に戻ってしまわないよう、じっくりと乾燥させます。その後、麻袋などに入れて保存し、仕上げ工場へと出荷されていきます。
仕上げ
乾燥が終われば「荒茶」の完成ですが、まだこの段階では製品として不十分なため、最後に「仕上げ」を行います。
8. 乾燥・火入れ
荒茶をじっくりと焙煎し、最終的な水分調整を行うとともに、好みの焙煎具合に仕上げることで、風味よく仕上げていきます。
これらの工程を経て、烏龍茶は完成となります。