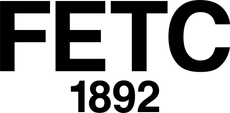最近よく見かけるようになった「プーアール茶」や「碁石茶」ですが、その独特の風味がどうやって生み出されているのかご存知でしょうか。実はある微生物の力を借りてその味や香りが生み出されています。微生物を使う製法から「プーアール茶」や「碁石茶」は「後発酵茶」とも呼ばれているのですが、一体なぜそのように呼ばれているのか、詳しく解説していきます。
後発酵茶の製造工程の特徴
「後発酵茶」とは、茶葉を発酵させる際に微生物を加えて発酵させることで作られるお茶をいいます。
一般にお茶の世界では「発酵」というと酸化発酵を意味し、この発酵は酵素の働きによって行われます。しかし、後発酵茶の「発酵」は微生物による働きをいい、いわゆるカビ菌や乳酸菌などが作用することで行われます。
使う菌による違い
後発酵茶では、麹菌のような酸素を好むカビ菌、乳酸菌のように酸素を嫌う菌の主に2パターンの菌を使い分けます。カビ菌だけを使うものに「プーアール茶」、乳酸菌だけを使うものに「阿波番茶」、カビ菌と乳酸菌の2つを使って二段階に発酵させるものに「碁石茶」などがあります。
後発酵茶の製造工程
「後発酵茶」の製造工程は使う菌ごとに違います。先ほど紹介した「プーアール茶」「阿波番茶」「碁石茶」もそれぞれの製法に違いがあります。この3つのお茶を例に解説していきます。
プーアール茶
「プーアール茶」はカビ菌を茶葉につけて数ヶ月以上発酵させて作ります。中には10年以上も熟成させたものもあり、熟成具合で味や効能も変化します。
1. 殺青(蒸熱)
収穫した茶葉を蒸気で蒸して、茶葉がもつ酸化酵素の働きを止めます。
2. 揉捻
熱いうちに揉んで、茶葉の水分を均一にし、茶葉の成分が出やすい状態にします。
3. 握堆(カビ付け)
カビ菌を加え、特定の温度・湿度管理を行いながら発酵させます。この工程の精度で品質や味・香りに差が出るため、重要な役割を担っています。
4. 乾燥
固まった茶葉をほぐして乾燥させれば、「プーアール茶」の完成です。
阿波番茶
「阿波番茶」は、元々桶などに住み着いている土着菌を利用して発酵させて作ります。
昔から徳島県で作られている個性的な郷土茶の一つです。
1. 殺青(茹でる)
収穫した茶葉を茹でて、酸化発酵が起こらないよう酵素の働きを止めます。他にも発酵の邪魔をする雑菌の繁殖を抑える効果もあります。
2. 揉捻
茶葉を揉んで、水分を均一にさせ、茶葉の成分が出やすい状態にします。
3. 漬け込み
揉捻後の葉を大きな桶に詰めて葉の茹で汁をかけ、上から突いて空気をしっかり抜きます。木の蓋を乗せ、その上から重石を乗せます。
この間に乳酸菌によって発酵が進み、大体2週間〜1ヶ月ほど漬け込まれます。
4. 乾燥(桶出し)
発酵が終わったら取り出して天日乾燥させます。その後、大きな茎などを取り除く選別作業を行えば「阿波番茶」の完成です。
碁石茶
「碁石茶」はカビ菌と乳酸菌の2種類を使い、二段階に発酵させて作ります。
高知県で江戸時代から作られており、今でもその製法が受け継がれています。
このお茶も土着菌の存在が欠かせず、昔から榁(むろ)やむしろに住み着いている菌を使います。
1. 殺青(蒸熱)
茶葉の収穫は、葉を摘むのではなく枝ごと刈り取っていきます。
枝ごと収穫した葉を蒸気で蒸して、茶葉のもつ酸化酵素の働きを止めます。
2. カビ付け
蒸し上がった茶葉をカビ付け室のむしろに広げて積み上げ、約1週間ほど寝かせて発酵させます。この間に乳酸菌が茶葉へ育まれていきます。
3. 漬け込み
カビが一面に生えてきたら、今度は桶に詰め替え、茶葉を蒸した時に出た汁をかけて重石を乗せます。ここで数週間漬け込むことで乳酸菌発酵がされます。
4. 裁断
発酵が終わったら固まりになったものを取り出し、3〜4cm角に専用の包丁で切っていきます。
5. 乾燥
切り終えたものむしろの上に並べ、天日乾燥させれば「碁石茶」の完成です。
茶葉は乾燥していくと黒く変化し、その色と茶葉の並ぶ様子が碁石のように見えることから、「碁石茶」と呼ばれるようになったと言われています。