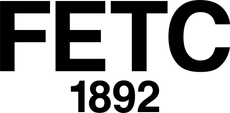千利休が侘び茶の祖と称されるのに対し、煎茶の祖と呼ばれるのが売茶翁(高遊外)です。煎茶を広めると同時に、当時の文化人に多大な影響を与えた売茶翁の生涯をご紹介します。
売茶翁とは
売茶翁の愛称で知られる高遊外(1675~1763)は蓮池藩(現佐賀県)の藩医の下に生まれ、黄檗宗龍津寺の化霖和尚の下で僧「月海元昭」となります。
50年近く修行に励んだ売茶翁でしたが、堕落した仏教界に失望し、僧をやめ京都に移り住みます。「茶亭・通仙亭」を開いた売茶翁は、風光明媚な場所に出向き茶を売る「移動販売」のようなこともしていました。
彼のもとには、その人柄に魅せられた文化人が集うようになり、この時から「売茶翁」と親しみを込め呼ばれるようになります。その後、僧侶としての名を捨て「高遊外」と名を変え売茶を続けますが、高齢となり体力の衰えを感じ売茶業を廃業し、89歳で生涯を閉じました。
エピソードから見る売茶翁
「高遊外」の由来
売茶翁は僧として「月海元昭」の名を持っていました。ある時、現在の暮らしぶりについて聞かれ「こういう具合に暮らしています。」と答えたところ、「こう優雅に暮らしています。」と聞き間違えられてしまいます。それを面白く思った売茶翁は「こう優雅に」の部分をもじり「高遊外(こうゆうがい)」と名乗ったといいます。
茶の良さを知ってもらうことが第一
通仙亭の看板には「茶銭は黄金百鎰より半文銭までくれしだい、ただにて飲むも勝手なり、ただよりほかはまけ申さず。」と書かれていました。
その意味は、「お茶代は、小判二千両(現在の一億円以上)から半文(現在の約30円)までいくらでもくれるだけ。 ただで飲んでも結構です。ただより安くはできません。」というものでした。
この文言からは、茶を飲んでもらい、茶の良さを知ってもらうことを第一に考えた売茶翁の姿勢が読み取れます。
新しいスタイルの「煎茶」を広める
売茶翁は、権力と結びつき形ばかりとなった当時の茶の湯を良しとせず、唐の陸羽(りくう)や廬同(ろどう)の「清風の茶」の世界を理想としました。
余計な作法や物を取り払い、シンプルに茶を楽しむ売茶翁の煎茶のスタイルは、庶民にまで広まっていきました。
最先端の文化人が憧れた売茶翁
江戸が日本の中心になった時代とはいえ、京都は依然、文化の最先端を行く大都市でした。
そんな地で売茶翁は、文化人達から絶大な人気を得ます。
売茶翁の教養の高さ、信念のもと自由に生活するスタイル、ウイットに富んだ語り口が人々を魅了したのです。その生き方や思想に影響された人の中には、伊藤若沖・与謝蕪村・渡辺崋山・松平定信・田能村竹田など、現在にも名を残す錚錚たる人物達がいたのです。
茶道具を自ら燃やす
売茶翁は高齢となり売茶業を廃業後、大切にしていた茶道具を自ら焼いてしまいます。それは、清貧の道を共に過ごした茶道具への愛情からでした。
「貧しく頼る人もいない私を支えてくれたのは、おまえ達(茶道具)だ。しかし、もうおまえ達を使うことができない。私が死んで、おまえ達が俗物の手に渡り辱められたら、私を恨むだろう。だから火葬にしてやろう。」と、売茶翁は、その気持ちを書き残していています。
茶道具への深い愛情が伝わるエピソードですが、茶道具が燃やされたことで「売茶翁の茶のスタイル」が後世に残らなかったことは大きな損失となりました。
売茶翁の目指した「茶」
売茶翁は浮世離れした仏教界から離れ、自活しながら精神的な高みを目指すことを選びました。その自活のための手段が「売茶」だったのです。そして、形骸化した茶の湯の世界に反発心を抱いた売茶翁が選んだ茶は「抹茶」ではなく「煎茶」でした。
売茶翁は、売茶の場を「サロン」にすることを目指したのではないでしょうか。事実、売茶翁の下には庶民から文化人まであらゆる人々が集い、茶を楽しむと同時にお互いを高め合う議論や交流が盛んに行われました。その中には、先にご紹介した名立たる画人・文人がいることを考えると、売茶翁の目論見は見事成功したといえるのではないでしょうか。
日常の雑事から離れ親しい人と談笑し茶を楽しむ時間の中に、売茶翁が追求めた人生の喜びや本質が見えてくるのかもしれません。