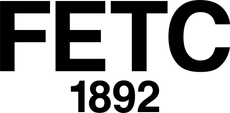私たちが普段飲んでいる緑茶・紅茶・烏龍茶など、味も香りも色も異なるこれらのお茶が、全て同じ茶葉から作られているのを知っていますか?
これらのお茶が異なる味わいや香りを持つのは、製造方法の違いによるものです。
今回は、なぜ紅茶が発酵茶と呼ばれるのか、紅茶の香りはどうやって生み出されるのかを、製造工程と共に解説していきます。
発酵茶(紅茶)の製造工程の特徴
発酵茶とは、酵素による発酵を完全に進めて作るお茶をいいます。
煎茶や深蒸し煎茶のような不発酵茶とは逆に、茶葉のもつ酸化酵素の働きを利用して、酸化発酵をさせるのが特徴です。
元々は約200年前に中国で生まれた「工夫製法(手作り製法)」でしたが、今では機械で作られることが多くなりました。
主な製法としては「オーソドックス製法」と「アン・オーソドックス製法」の二つがあり、さらにこの二つを組み合わせた製法も生み出されています。
ここでは、伝統的な「オーソドックス製法」をご紹介します。
発酵と酸化?
お茶の世界で使われる発酵とは、味噌やヨーグルトのように微生物(菌)によって起こる発酵とは違い、茶葉のもつ酸化酵素よって起こる酸化のことを指しています。
酸化とは、酸素と酵素が結びついて、元の成分を変化させる反応をいいます。
一部、後発酵茶のように微生物の力で発酵させるお茶もありますが、基本的にお茶業界では、この酸化発酵を発酵と呼んでいます。
収穫された生葉が出荷されるまで
収穫時期になると茶葉は摘み取られ、摘み取られた生葉は揉みや乾燥の工程を行った「荒茶」へと加工されます。その後「仕上げ」を行い、製品として出荷されていきます。
荒茶ができるまで
生葉は摘み取られた後「萎凋 → 揉捻 → 玉解き・ふるい分け → 発酵 → 乾燥」という工程を経て「荒茶」へと加工されます。
1. 萎凋

生葉に含まれている水分を均一に取り除くため、しおれさせていく作業を萎凋と呼びます。
以前は日陰干しが多かったのですが、現在は萎凋槽を使って大量の温風でしおれさせる「人工萎凋」が行われています。
2. 揉捻

茶葉の細胞を破壊し、葉の中の酸化酵素の働きを促して形を整えていきます。
酸化酵素が空気中の酸素に触れると活性化し、カテキンやペクチン、葉緑素が酸化発酵します。この酸化酵素こそが、紅茶の香り・味・コク・水色を作る重要な要素であり、紅茶と緑茶の違いへと繋がります。
この工程では大体45〜90分発酵させますが、酸化発酵が一気に進みすぎないように発酵を抑える目的で玉解機にかけ、冷却してから再び揉む作業を繰り返します。
3. 玉解き・ふるい分け

揉捻で茶葉は塊になるので、これを解いて平均的に空気に触れるようにし、酸化発酵をさらに促進していきます。この工程では20〜30分ごとに玉解機にかけます。
機械のメッシュで茶葉をふるい、下にふるい落とされたものは「ふるい下」といい、次の工程に移します。ふるいに残った大きい葉は「ふるい上」といって再び揉捻の工程に戻されます。
4. 発酵

室温25〜26度、湿度90%の発酵室に、厚み4〜5cmほどに均一に広げ、2〜3時間放置します。この工程の間に、緑色だった葉が鮮やかな赤銅色になり、紅茶らしい香りも漂い始めます。
ただし、発酵しすぎると紅茶本来の香りが台無しになってしまい、水色も黒っぽくなるため、発酵を止めるタイミングを見極める必要があります。
5. 乾燥
発酵終了時の茶葉はまだ水分が多く、そのままだと発酵が続いてしまうため、乾燥機に入れて100度前後の高温熱風で乾燥させます。乾燥させることで酸化酵素を失活させ、水分を5%以下にまで減らしていきます。
仕上げ
乾燥まで終えると「荒茶」は完成しますが、「荒茶」ではまだ製品として出荷できません。そこで「仕上げ」として「選別・整形 → ブレンド」を行うことで、ようやく製品として出荷することができます。
6. 選別(等級分け)
荒茶を何度もふるいにかけ、大きさや葉の形で選別します。この選別によって茶葉は等級に分けられていきます。この等級を「リーフグレード」といいます。
7. ブレンド
最後に茶葉をブレンド(配合)します。約20種類以上の茶葉を使いますが、様々な種類を混ぜるのではなく、同じ産地内のものを合わせて品質を安定させるのが目的です。ブレンドが紅茶の価値を左右するため、いかに消費者の好みにあったブレンドを行えるかがポイントになります。