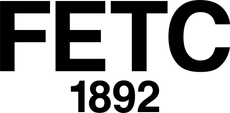私たちが普段飲んでいる緑茶・紅茶・烏龍茶など、味も香りも色も異なるこれらのお茶が、全て同じ茶葉から作られているのを知っていますか?
これらのお茶が異なる味わいや香りを持つのは、製造方法の違いによるものです。
今回は、「緑茶(煎茶)」や「深蒸し煎茶」が、どういった製法で作られているのか、また緑茶と深蒸し煎茶の違いは何かを解説していきます。
不発酵茶(緑茶)の製造工程の特徴
不発酵茶とは、茶葉のもつ酵素が行う発酵(酸化)を、加熱によって失活させて(酵素の働きを止めて)、発酵をさせずに作るお茶をいいます。他の発酵茶にはない「失活」を行うことが不発酵茶の特徴です。
不発酵茶として代表的なのが緑茶(煎茶)ですが、元々日本のお茶は緑色ではなく黄色や茶色をしていました。しかし、「青製煎茶製法」の発明により、今のような美しい緑色の水色の、上品な甘みと香りの生きた緑茶が生まれました。
収穫された生葉が出荷されるまで
収穫された生葉は、まず産地の近くで揉みや乾燥を行った「荒茶」という状態にまで加工されます。その後、さらに「仕上げ」加工が行われ、製品として各地へ出荷されていきます。
荒茶ができるまで
荒茶は、美味しい緑茶を作るための「下準備」のような役割を担っています。荒茶は「摘採(生葉を収穫すること)→ 蒸熱 → 粗揉 → 揉捻 → 中揉 → 精揉 → 乾燥」という手順を踏んで完成します。
1. 蒸熱
生葉を蒸して酸化酵素を失活させます。
圧力をかけずに均等に蒸気で蒸すことで、茶葉を緑色に保ちつつ、青臭みを取り除いていきます。緑茶において、この工程はとても重要で、蒸し時間の長さによって色や香り・味などが決まります。蒸し時間を長くすると、色は濃くなり、渋味と香りは少なくなります。
2. 粗揉

強い力で揉み、適度な圧力を加えながら、熱風を当てて乾かします。茶葉を柔らかくし、茶葉のもつ水分を減らすための工程です。
3. 揉捻

粗揉だけだと揉み足らないため、今度は加熱をせずに圧力だけで揉みます。茶葉の水分を均一にしていくとともに、細胞を破壊し、茶葉の成分が出やすいようにします。
4. 中揉
揉捻後の茶葉は縮んで形も不揃いなため、中揉工程では熱風を当てながら茶葉を解きほぐし、次の精揉をしやすいよういに細長い形に整え、さらに揉みます。
5. 精揉

茶葉の乾燥を促しつつ、一定方向にだけ揉みます。この工程で緑茶独特の針のような細長い形ができあがります。
6. 乾燥

精揉後の茶葉ではまだ水分を10〜13%含んでいるため、さらに念入りに熱風乾燥させて5%程度にまで下げます。これで「荒茶」の完成です。
仕上げ
荒茶の状態では、まだ形が不揃いで水分が多く、品質の維持が難しいため、その後「仕上げ」加工を行います。「仕上げ」工程は、「先火 → 選別・整形 → 火入れ → 合組」の順に行われ、計量や検査・包装を経て出荷されます。「仕上げ」を行うことで、長期保存が可能になり、お茶の香味をよりよくする効果もあります。
7. 先火
選別や整形を行う前に、荒茶全体にまず火入れ(焙煎など)をします。
8. 選別・整形

火入れ後の荒茶をふるいにかけ、細かい茎などを取り除き、葉の大きさで選別します。さらに切断などの加工を行い、形を整えます。
9. 火入れ

最後にもう一度火入れして乾燥させることで、保存性を高めるだけでなく、お茶の香りを引き出します。
10. 合組

最終調整として製品の配合や品質を均一にするために「合組(ブレンド)」を行います。合組を行うことで、バランスのいいお茶に仕上がります。
深蒸し茶って?
深蒸し茶は、通常の「煎茶」より、蒸し(蒸熱)時間を2〜3倍長くして作られた煎茶のことをいいます。 それ以外の工程は通常の煎茶とほぼ変わりはありません。
長く蒸す分、茶葉がより柔らかく、崩れやすくなるため、通常の煎茶と比べて茶葉の形が細かいのが特徴です。
茶葉が細かくなると、お湯に触れる面積が広くなり、成分が抽出されやすくなるため、淹れる際は通常の煎茶よりも抽出時間を短くします。
深蒸し煎茶にする理由
深蒸し茶は、通常の「煎茶」は、渋みと甘みの調和が取れており、淡い緑の水色が特徴的ですが、品種や生産地によっては渋みが強く出るものもあり、消費者の口に合わないこともありました。
そこで、渋味を減らしてお茶の甘味をより引き立たせるために、茶葉を深く蒸すようになったのです。深く蒸したことにより茶葉はさらに細かくなり、水色に緑が濃く出るようになりました。この水色の鮮やかさも評判になり「深蒸し茶」はたちまち人気となりました。