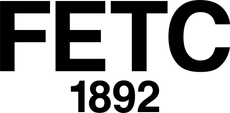普段飲んでいるお茶が、どのような製造工程を経て私たちのもとに届くのかご存じでしょうか?この記事では、生葉の収穫から出荷までの主なプロセス、お茶作りに欠かせない「荒茶」と「仕上げ」の違い、そして緑茶・紅茶・烏龍茶など茶種による製法の違いについて、わかりやすく解説します。お茶の魅力をさらに深く知りたい方に向けた、完全ガイドです。
収穫された生葉が出荷されるまでの主なプロセス
お茶の葉は茶園で育てられ、摘み取りの時期を迎えると生葉が収穫されます。その後、さまざまな製造工程を経て、全国各地に出荷され、私たちのもとに届けられます。お茶の製造工程は茶種によって多少異なりますが、基本的な流れは「荒茶」づくりと「仕上げ」の2段階に大きく分けられます。この2つの工程について、順番に見ていきましょう。
荒茶ができるまで
荒茶とは、仕上げ加工を行う前の段階まで整えられた茶葉のことを指します。収穫された生葉は、まずこの荒茶の状態まで加工され、出荷直前まで保管されます。
お茶の生葉には酸化酵素が含まれており、摘み取った直後から酸化(発酵)が始まります。発酵させずに作る緑茶などでは、生葉の酸化を防ぐために、摘採後すぐに加熱処理を施して酵素を失活させます。その後、揉捻・精揉・乾燥といった工程を経て、荒茶が完成します。
一方、紅茶のように発酵させて作るお茶では、萎凋(しおれさせる工程)や揉みを経た後、高温多湿な発酵室で十分に酸化を進めます。発酵を終えた後に乾燥を行い、荒茶として仕上げます。
発酵(酸化)
お茶の生葉には酸化酵素が含まれており、摘み取った直後から酸化(発酵)が始まります。この発酵とは、酸化酵素の働きによるものであり、微生物による発酵とは異なります。ただし、後発酵茶のように、微生物の働きで作られるお茶も一部存在します。
失活
失活とは、加熱処理などによって茶葉に含まれる酵素の働きを止める工程です。これにより酸化(発酵)を防ぎます。代表的な方法として、「蒸し製(蒸気で加熱する方法)」と「釜炒り製(釜で炒る方法)」があります。
揉捻
揉捻は、茶葉に圧力を加えながら揉む工程です。これにより茶葉内の水分が均一になり、成分が抽出されやすくなります。また、茶葉の形を整える役割もあります。
精揉
精揉は、茶葉に熱を加えながら一定方向に揉み込む工程です。乾燥と成形を同時に行うことで、細く美しい茶葉の形に整えます。
乾燥
乾燥は、茶葉に熱風をあてて念入りに水分を飛ばす工程です。ここで茶葉の保存性が高まり、製品としての品質が安定します。
仕上げ
荒茶の状態では、茶葉の形が不揃いで水分も十分に抜けきっていないため、そのままでは製品として出荷できません。ここから「仕上げ」と呼ばれる工程を行い、品質を整えます。仕上げは、選別・整形 → 火入れ → 合組(ブレンド)の順に進められ、最終的に計量・検査・包装を経て出荷されます。この工程によって、お茶の保存性が高まり、香りや味わいもより一層引き立ちます。
選別・整形
まず、荒茶をふるいにかけて細かい茎や粉を取り除き、葉の大きさごとに選別します。その後、必要に応じて茶葉を切断するなどの加工を施し、形を整えます。これにより、製品としての見た目が美しく揃えられます。
火入れ
選別・整形が終わった茶葉に、もう一度火入れ(加熱乾燥)を行います。火入れをすることで、茶葉の保存性が向上すると同時に、お茶本来の豊かな香りが引き出されます。火入れの温度や時間は、茶種や狙う風味によって調整されます。
合組(ブレンド)
合組とは、複数の荒茶をブレンドして、味や香り、品質を均一に整える工程です。合組によって、製品ごとに理想的な味わいが作り上げられます。合組後、計量・検査・包装を経て、ようやく製品として出荷されます。
茶種による違い
お茶の製造工程は、茶葉の発酵(酸化)の進み具合によって異なり、「不発酵茶」「半発酵茶」「発酵茶」「後発酵茶」の4つに大きく分類されます。また、それらをベースにして花や果実で香りづけを施した「花茶」もあります。ここでは、それぞれの特徴と製法の違いについて解説します。
不発酵茶(緑茶・抹茶など)
不発酵茶とは、生葉を摘み取った直後に加熱処理を施し、酸化酵素の働きを止めることで発酵を防いだお茶です。代表的なものに緑茶や抹茶があります。発酵しないため、鮮やかな緑色と爽やかな香りを保ち、加熱によって引き出される香ばしさとともに、上品な味わいが楽しめます。
半発酵茶(烏龍茶など)
半発酵茶は、適度なところで発酵を止めて作られるお茶です。まず生葉を萎れさせ、酸化酵素の働きで香気成分を作り出し、独特の芳香を生み出します。発酵の度合いによってさらに細かく分類され、「白茶(パイチャ)」「黄茶(ファンチャ)」「青茶(チンチャ・烏龍茶)」などがあります。緑茶と紅茶の中間的な味わいが特徴です。
発酵茶(紅茶)
発酵茶は、摘み取った生葉をしおらせ、十分に酸化酵素を働かせてから作られるお茶です。半発酵茶よりも発酵度合いが高く、華やかな香りと深いコクが特徴です。世界中で最も多く消費されているお茶のスタイルがこの発酵茶(紅茶)です。
後発酵茶(プーアル茶など)
後発酵茶は、摘採後の茶葉を、酸化酵素ではなく微生物の働きによって発酵させるお茶です。微生物の種類によって風味が大きく異なり、たとえば麹菌による発酵では中国の「プーアル茶」、乳酸菌による発酵では日本の「碁石茶」などが知られています。熟成によって味わいがまろやかに変化していくのが特徴です。
花茶(ジャスミン茶など)
花茶は、緑茶や白茶、青茶などの茶葉に、花や果実の香りを移して作られるお茶です。代表的なものはジャスミン茶で、上品な香りとすっきりとした味わいが特徴です。日本でも親しまれており、リラックス効果のあるお茶として人気があります。