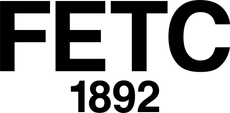お茶を淹れた後の出がらしの茶葉、そのまま捨てていませんか?
実は茶葉は美味しく飲めるだけでなく、そのあと食べることもできるんです。
ここでは溶け残った豊富な栄養素を丸ごと摂ることができる「お茶のおひたし」の作り方をご紹介します。
出がらしのお茶は食べられる?

出がらしの茶葉は食べられると聞いて驚かれるかもしれませんが、茶産地である京都府や静岡県ではよく食べられており、珍しいことではありません。
出がらしといっても味や香りが全て出尽くしているわけではないので、口に入れた瞬間にふわっとお茶の味と香りが広がります。特に玉露などの高級茶の茶葉は苦味もなく、コクや旨味も残っているので意外にも美味しく食べられるのです。
お茶のおひたしの作り方

近年は健康志向ブームで出がらしの茶葉を使ったレシピが数多く存在しますが、今回はその中でも特に簡単な「お茶のおひたし」の作り方をご紹介しましょう。
材料

- 出がらしの茶葉:適量
- 醤油:少々
手順
①急須から取り出した茶葉をキッチンペーパーなどに包んで水分を軽く取ります。

②茶葉を小皿に盛り、醤油を数滴たらして完成です。

醤油以外にも、ポン酢やめんつゆで作っても美味しいですし、鰹節・ごま・すりおろし生姜・唐辛子・塩など薬味を加えてアレンジしても美味しく食べることができます。
苦味が気になる方は、2.3煎出した後の茶葉を使えば苦味が減って、さっぱりした味わいになります。
おひたし以外でも、ふりかけにしたり、チャーハンに混ぜたり、佃煮にしたり、シフォンケーキなどの生地に混ぜて使ったりと使い道はたくさんあります。
お茶をおひたしで食べるメリット
茶葉には栄養素が豊富に含まれていますが、その栄養素は水に溶ける「水溶性」と油に溶ける「脂溶性」の2つに分けられ、お茶の栄養素の約7割が脂溶性です。
水溶性の栄養素であるカテキン・カフェイン・テアニン・ビタミンCも、その全てがお湯も溶け出す訳ではなく、お茶の豊富な栄養素の7割以上が茶葉に残ったままの状態なのです。
ちなみに茶葉に含まれる脂溶性の栄養素はβカロチン・ビタミンA・ビタミンE・クロロフィル・食物繊維などがあり、特に血行を改善してくれるといわれているビタミンEは、ほうれん草の25倍も含まれています。
茶葉を直接食べることで、水に溶けずに茶葉に残った豊富な栄養分を丸ごと摂ることができるのです。