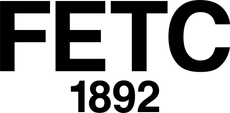福岡県は、最高級のお茶・玉露の生産が盛んな茶産地です。2020年の生産量は1,600トンと、国内6位の生産量を誇ります。
“やぶきた”を中心に”かなやみどり”、”おくみどり”、”さえみどり” 、“あさつゆ”などの品種が栽培されています。
生産される茶種は、煎茶・かぶせ茶・玉露・釜炒り茶など様々ですが、特に伝統本玉露の生産量は日本一を誇り、日本屈指の高級茶の産地でもあります。
福岡県のお茶の特徴
伝統本玉露で知られる福岡県では、玉露以外にもさまざまな種類のお茶が作られています。
地域によって差異はありますが、毎年日本全国数十件の生産者とお会いする私たちが感じる福岡のお茶の特徴をご紹介します。
1kg30万円?最高級の玉露の産地

玉露は、最高級のお茶とされており、摘採前に20日間以上の被覆栽培を経て作られます。
かぶせ茶が10日前後の被覆栽培で作られるのに対し、その期間は倍以上。
福岡県八女市の「八女伝統本玉露」は、一般的な黒い寒冷紗ではなく、藁やよしずの覆いをかける「覆下」という伝統的な栽培方法で作られています。
手摘みで作られるため、生産量も極めて少なく、その分値段も他のお茶とは一線を画します。その年の品評会で最高の評価を得たものは1kg30万円の値がつくことも。
名実ともに、日本最高級のお茶です。
旨味のお茶作り
長年玉露を作ってきた経験からか、福岡県の煎茶は、旨味を楽しむお茶が非常に多いのが特徴的です。
日本のお茶の7割を占める”やぶきた”や、玉露に使われることもある”さえみどり”、天然玉露とも呼ばれる”あさつゆ”や、すっきりとした味わいの”おくみどり”など、濃厚な旨味を楽しめるのも、福岡のお茶の特徴です。
福岡県のお茶づくりの歴史
福岡県のお茶づくりは、県の南西部にある八女市で始まりました。
室町時代、周瑞禅師が筑後国上妻郡鹿子尾村(現在の黒木町笠原)に霊巌寺を建て、中国から持ち帰ったお茶の種を蒔いたといわれています。
同時期に、釜炒り茶の栽培や製造などを、鹿子尾村の庄屋である松尾太郎五郎久家に伝えたと言われており、これが福岡のお茶づくりの発祥となりました。
江戸時代の中期には、八女から京都や大阪へ、少量ながらも釜炒り茶が流通するようになりました。
ただし、当時はまだお茶の生産量が少なかったため、ほとんどのお茶は久留米藩内での流通に留まっています。
現在の八女茶最大の特徴である玉露が生まれたのは、明治時代の初期といわれています。
山門郡(現在のみやま市)にある清水寺の住職・田北隆研によって、玉露の栽培法や製茶法を教えるための修練所が作られ、玉露の生産が普及しました。
その反面釜炒り茶は、明治20年(1887年)アメリカが出した粗悪茶輸入禁止条例により、輸出量が激減。その後国内市場に置いても釜炒り茶よりも通常の蒸製緑茶の人気が高まった結果、釜炒り茶の生産は次第に縮小していきました。
その後、大正時代には煎茶の製造技術も発達し、複数存在していた郡産茶を「八女茶」のブランドの元に統合し、現在の八女茶に続きます。
福岡県のお茶の産地
福岡県の茶園の約90%は八女地域にあり、その全てを「八女茶」と呼んでいます。
伝統本玉露の「八女茶」
福岡県の南西部にある八女市と、その隣にある筑後市、広川町などで作られるお茶です。
主に煎茶が作られていますが、山間部では玉露も生産されています。
八女の玉露は、日本でも最大級の生産量を誇り、全国茶品評会でも19年連続で入賞するなど、非常に高い評価を得ています。八女の玉露は、生産量・質ともに、日本トップクラスのお茶です。
清らかな湧水と山間部のうきは市

県の南西部に位置するうきは市は、名水百選に数えられる湧水があり、今も上水道の設備を持たず、豊かな地下水と湧水で人々が暮らす、自然豊かな街です。
豊かな水源に支えられ、山間部に作られたうきはの畑では、香り高く仕上げられたお茶が作られています。