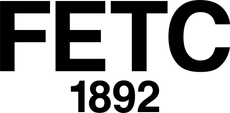“やぶきた”という名称を聞いたことがないあなたでも、知らないうちに必ず飲んでいるお茶。それが日本一生産されている緑茶の品種、”やぶきた”です。
ここでは日本で最もメジャーなお茶の品種、”やぶきた”をご紹介します。
“やぶきた”は緑茶のスタンダード

日本で登録がされているお茶の品種は、2019年時点で119品種。その中でも国内で作られる緑茶の75%以上は”やぶきた”です。(2020年現在)

“やぶきた”の発祥地であり、日本全国に広まるきっかけとなった静岡県ではそのシェアはさらに大きく、90%にものぼります。
もちろん同じ品種でも栽培する土地、育て方、加工法などで多少味が変わるので、「同じ品種=全く同じ味」というわけではありません。
“やぶきた”の特徴
ここまで”やぶきた”が日本中で栽培されるようになった理由は、数々の優れた特徴にあります。
煎茶、碾茶、玉露。あらゆる茶種に適した「品質の高さ」

“やぶきた”は非常に品質が高いことが何よりの特徴です。
肥料や被覆栽培で旨味が乗りやすく、煎茶、碾茶(抹茶の原料茶)、玉露、釜炒り茶など、あらゆる茶種に適性がありました。特に煎茶としての品質は「極めて優れている」と評価されています。
クセがなく青青しいフレッシュな香りを持ち、味は旨味・渋味・苦味のバランスが良く、万人に好かれる味わいです。
強い耐寒性からくる「育てやすさ」

煎茶としての品質に優れた”やぶきた”ですが、非常に育てやすい品種でもあります。
広域適応性品種なので地域を選ばず全国どこでも栽培することができ、南は沖縄から北は新潟まで、日本のあらゆる地域で栽培されています。
お茶は一番茶萌芽後の寒さや霜害に最も警戒しなければならないほか、寒さの厳しい地域では冬季に枯れてしまうこともありますが、”やぶきた”は寒さにも強く、寒さで葉の色が変わったり、枯れたりする凍害を受けにくいのも強みです。
病気や虫害に弱いという特徴はありますが、農薬や畑を作る場所によって克服できるため、日本全国どこでも安定して作れる品種なのです。
安定した品質

今でこそお茶は挿し木で育てるのが普通になっていますが、昔は種を植えて1から育てていました。これを「実生」といいます。
実生の茶樹は育て方などによって品質にばらつきが出てしまい、茶農家が頭を抱えていたところに登場したのが、安定して高品質のお茶が育つ”やぶきた”でした。
お茶は収穫まで3〜10年、植え替えは30〜50年に1度程度とされています。
作物として非常に長いリードタイムを要するお茶の場合、品種選びは茶園の運命を左右する大事な作業。そんな折、安定して高品質なお茶が採れる”やぶきた”に人気が集まったのは必然ともいえます。
生産者の収入に直結する「収量の多さ」

“やぶきた”はもともと収量が多い品種なうえ、凍霜害を受けにくい時期に萌芽するため、他の品種に比べ、安定して多くの収量を望むことができます。
育てやすく、品質も高くて、たくさん収穫できる。それがやぶきたの特徴であり、ここまで日本中に広まった理由です。
品質や収量が安定する分、茶商も仕入れがしやすく、買い手にも困らないことから、1970年代に爆発的に普及し、現在においても不動のトップシェアを誇る、緑茶の超王道品種なのです。
やぶきたの歴史
やぶきたの歴史は1908年(明治41年)に静岡で発見されたことで始まります。
やぶきたとやぶみなみ
当時お茶の研究家だった杉山彦三郎(1857年〜1941年)は、静岡県静岡市で竹やぶを開拓して茶園を作り、お茶に関する様々な研究を進めていました。
ある時、その茶園で優良な茶の木、2本が選抜されました。
選ばれた2本のうち、竹やぶの北側に植えられていた茶の木が「やぶきた」と名付けられ、竹やぶの南側に植えられていた茶の木は「やぶみなみ」と名付けられました。
観察と実験を続けた結果、”やぶみなみ”よりも優良だった”やぶきた”一本に絞り、そこから品種改良を重ねて出来たのが、”やぶきた”です。
一気に広がった昭和時代
何年もの研究の末に生まれた“やぶきた”ですが、実はこの品種、誕生後すぐに高い評価を得られたわけではありませんでした。
茶畑の改植はお金も時間もかかる作業ですし、”やぶきた”が誕生した当時、また「お茶の品種」という考え方は非常に新しく、先祖代々の畑で変わらずお茶を作る生産者が多かったのです。
杉山彦三郎の死後10年以上が経った戦後にやっと高い評価がつきはじめ、1945年に静岡県の奨励品種に指定されたり、1953年に農林水産省の登録品種になったりしたことで、一気に全国に広まり、972年には品種茶園の88%がやぶきたとなりました。
現在は静岡の天然記念物に
100年以上前に発見され、緑茶の歴史を作ったやぶきたの母樹は実は今も存在し、元気に青々とした葉をつけています。
静岡県の天然記念物に指定されたやぶきたの母樹は樹齢110年を超える老木となり、現在は地元の人やお茶好きの観光客などがこの母樹を見に集まっています。