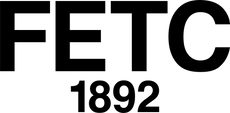茶器|磁器
この記事では、焼き物の中でも「磁器」についてご紹介します。
磁器って?
磁器は白く半透明で表面の肌理が細かく、つるつるとした手触りの焼き物。ガラス質が多く含まれているので光に当てると少し透き通る場合もあります。
磁器の原料である土に多く含まれる長石や珪石は、高温で焼き締めることで結晶化し、とても硬くなる性質を持っているので、陶器に比べて丈夫で薄くて軽い焼き物を作ることができるのが磁器の特徴。
また、磁器でできた茶器は吸水性がなく表面がツルツルしているため、お茶の香りや成分が茶器に吸着しにくく、茶葉が持つ本来の味や香りをそのまま出すことができます。
手入れが簡単で、コツなしで美味しいお茶が淹れられる茶器として初心者には特におすすめです。
日本の磁器
日本の代表的な磁器をご紹介しましょう。
有田焼
有田焼は佐賀県の有田町周辺の地域で生産されている焼き物。
今から400年前に日本で初めて磁器を作ったのがこの有田焼で、世界的に有名なブランド「マイセン」にも影響を与えたといわれています。
有田焼は透き通るような白磁にさまざまな色で鮮やかに絵柄がつけられており、特にヨーロッパでは昔から現在まで「IMARI」という愛称で高い人気を誇っています。
磁器は基本的に複数の土を配合して焼くのですが、有田焼は1種類の陶石のみを使って作られる世界的に見ても非常に珍しい磁器で、特に透明感のある白磁は「白い金」と称えられ、世界中から高い評価を得ています。
九谷焼
九谷焼は石川県の金沢市・加賀市・美濃市・小松市で生産されており、磁器だけでなく陶器も作っています。
宮内庁が海外の著名人や皇族への贈答品として使っており、イギリスのチャールズ皇太子の結婚祝いとしても献上された由緒正しき焼き物。
九谷焼は「上絵付けを語らずして九谷はない」と称されるほどの日本を代表する色絵陶磁器で、華やかな茶器も有名です。
上絵付けとは、本焼きした後に顔料で絵をつけ、約800度の高温で焼きなおす技法のことで、焼きなおすことで作品に唯一無二の味のある模様がつきます。
また、九谷焼の上絵付けは「赤、黄、紫、緑、紺青」の色彩を使うことから五彩手と呼ばれ、その豪華爛漫な大胆な色合いと絵付けは一度見たら忘れられません。
波佐見焼
波佐見焼は長崎県にある波佐見町とその付近で作られています。
焼き物と聞くと高級なイメージがありますが、波佐見焼は日常的に使う庶民的な食器などを作っており、日本の日用食器の20%弱が波佐見焼の食器です。
波佐見焼にはこれといった技法がなく、さまざまな作家がその時代に求められる形・デザインの焼き物を柔軟に作っているので、デザインも大きさもバラエティーに富んでいます。
見た目のお洒落さと、専門店だけではなく食器屋や雑貨屋などでも気軽に購入できることから、最近はもともと焼き物に興味を示さなかった若い世代から支持を得て話題になっています。